人は寝ないと生きていけない。あたり前のことだけれど、その重要さを、私たちはどれだけ意識できているのだろう?睡眠は健康の土台であり、仕事にも私生活にも大きな影響を及ぼす大切な機能なのだ。言い換えれば、眠りを制すればQOLも上がるはず。9月3日は「ぐっすりの日」。この機会に、睡眠についてあらためて知っておこう!
正しい睡眠の知識を
アップデートしよう!
遊びや仕事のために夜の睡眠時間を削っている人は多いのではないだろうか。「日本人のほとんどは睡眠不足」と睡眠研究の第一人者、柳沢正史教授は警鐘を鳴らす。
「日本人の平均睡眠時間は欧米の先進国と比べて1時間くらい短い※。睡眠不足になると、あらゆる面でパフォーマンスが落ち、病気になるリスクも上がります」。睡眠時間を削ってまで行う仕事は非効率で、プライベートにも影響が出る可能性がある。柳沢教授は睡眠に関する間違った情報が出回っていることも危惧している。
「たとえば、 “成長ホルモンが出る午後10〜午前2時が睡眠のゴールデンタイム”、というのは間違った認識です。時刻に関係なく夜の前半の深いノンレム睡眠中に成長ホルモンは出ます。睡眠はノンレム睡眠(深睡眠)とレム睡眠(鮮明な夢をみる)がありますが、夜の後半に増えるレム睡眠も極めて大切で、睡眠時間のすべてがゴールデンタイムといえます」
また、朝型と夜型の考え方も間違って伝わっていることが多いという。
「朝型か夜型かは遺伝子レベルで決まっていて、自分の力では変えられません。でも世の中の仕組みとしては朝型中心。夜型の人には不利にできています。夜型への理解が進み、それぞれの体質に合わせたフレックスタイムが採用されたほうが、生産性も上がるし健康な人も増えるはずです。じつは人間は、哺乳類の中でいちばん深く続けて寝る能力を持っている。そしてその能力が、人間の高度な思考を実現させている可能性があります。睡眠は、進化の過程で獲得したギフトでもあるのです」
そのギフトをしっかり享受すれば、本来の力を最大限に発揮できるはず。まずは自分の睡眠時間を見直してみよう!
※経済協力開発機構(OECD), Gender data portal2021より

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(IIIS)
機構長・教授
柳沢正史さん
医学博士。株式会社S’UIMIN代表取締役。筑波大学医学専門学群・大学院医学研究科博士課程修了後、テキサス大学サウスウェスタン医学センター及びハワードヒューズ医学研究所にて24年間にわたり研究室を主宰。2010年筑波大学に研究室を開設し、2012年国際統合睡眠医科学研究機構創設。生命科学ブレークスルー賞、クラリベイト引用栄誉賞など受賞歴多数。『今さら聞けない 睡眠の超基本』(朝日新聞出版)など監修書・著書多数。
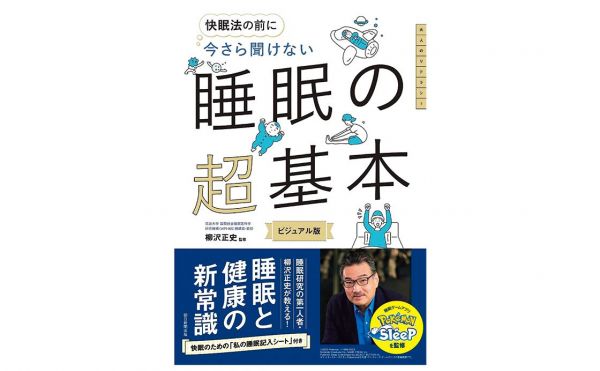
寝ている間に
何が起きている?
一般に、眠っているときには脳は休息をとっていると勘違いされていますが、眠っている間でも脳は活動し、メンテナンスや記憶の整理などを行っています。睡眠中は身体全体でも細胞の修復(疲労回復)、免疫システムの強化、代謝の調整などをしています。睡眠不足ではこうした働きがすべて阻害され、記憶力の低下や抑うつ不安、メタボ、感染症などの罹患リスクが高まり、あらゆることにネガティブな影響が出てきます。
睡眠はまず量を確保!
どんなに質のいい睡眠をとっても、十分な睡眠時間がなければ意味がありません。いちばん大事なのは「睡眠量」の確保なのです。1日1時間の睡眠不足を補うためには、約4日間かかります。休日は平日より2時間以上多めに眠ってしまう人は慢性的な睡眠不足の可能性があります。毎晩30分でも睡眠時間を増やすことで肉体面・精神面ともに調子のよさを実感できるはずです。
じつは日本は
世界一の寝不足国
睡眠に関するあらゆる調査で、日本は国民の睡眠時間が最も短い国のひとつであることがわかっています。日本人の睡眠時間は1960年では8時間13分でしたが、それから55年間少しずつ減り続け、2015年では7時間15分に。夜10時までの就寝率も、1960年では67%だったのに対し、2015年では27%まで減少しています※。
※NHK国民生活時間調査,2015より
睡眠不足はタイパが悪い
日本では睡眠不足が原因で仕事のパフォーマンスが低下し、年間約15兆円もの経済損失が生まれているという試算※があります。国民一人あたりのGDPが高い国ほど平均睡眠時間が長いという調査結果※も。睡眠不足になるとコミュニケーション力や理解能力、他人への共感能力が低下し、ちょっとしたことでもいらだって人間関係にも悪影響が出てしまいます。本来の力を発揮するためにも、睡眠時間をしっかり確保しましょう。
※米ランド研究所の調査資料, 2016より
※公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較2021」より
自分の睡眠を見える化しよう
睡眠に関する問題は無自覚なことが多く、根が深いものです。いまは睡眠時の心拍数や呼吸を解析するデバイスなど、睡眠を客観的に測って可視化する方法がさまざまあるので利用してもいいでしょう。でも睡眠状態を正確に把握するためには、脳波の計測が必要です。主観的にはしっかり眠れていると感じていても、脳波を測ると眠りの質が悪いことも。主観性と客観性が一致しないこともよくあるので、脳波計測による睡眠の可視化は重要です。

柳沢教授が起業した「S’UIMIN」社でも、睡眠時の脳波を測定してAIで解析し、医師による改善アドバイスを加えて利用者にレポートする、睡眠測定サービスを展開している。
早寝早起きが
いいとは限らない
朝型か夜型かは遺伝子によって決まります。生体リズムを司る体内時計の周期が朝型の人は24時間より短く、夜型の人は24時間より長いという個人差があります。年齢によっても2時間ほど体内時計は変化します。10歳頃までは朝型で、10〜30代前半では夜型傾向になり、40〜50代では朝型に戻ってゆき、70代では超朝型傾向になります。多少のずれは生活環境を整えたり、朝日を浴びて体内時計をリセットするなどして調整できますが、大幅な変更はできません。
自分にベストな
睡眠時間は?
4日間連続で休みが取れたら、最適な睡眠時間が調べられます。4晩続けて眠れるだけ眠ってみてください。睡眠負債を抱えている場合、1日目はたくさん眠れます。2日目から徐々に睡眠時間が短くなり、4日目にその人の本来の睡眠時間に落ち着きます。また、平日3〜4日続けて就寝時間を30分早め、身体の調子が上がればさらに15分ずつ早めていく方法もあります。朝、自然に目覚められるところが最適な睡眠時間です。
暗くて静かで
朝まで適温が大切
よく眠れる環境づくりのポイントは、光、音、温度の調整です。夜に光があるとメラトニンという睡眠ホルモンの分泌が抑制されて寝つきが悪くなるため、夜は間接照明にして眠るときは真っ暗にするのが理想的です。音は、とくに覚醒作用の強い人の話し声が耳に入らないように注意し、静かな環境を用意すること。室温は、冬は19〜22度、夏は23〜26度が適温。エアコンなどを使用して朝まで適温を保つことが重要です。

![まずは知っておこう睡眠の超基本[ぐっすり快眠]](https://images.metropolitana.tokyo/1917/2567/3259/metro259_special_01_hdr.jpg)
![まずは知っておこう睡眠の超基本[ぐっすり快眠]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/1917/2567/3259/metro259_special_01_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》癒やされる宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5217/7077/4672/metro276_jreast-takaramono-03_hdr.jpg)
![《目的別で見つける東北の宝もの》食べる宝もの6選[東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6017/7062/3201/metro276_jreast-takaramono-02_hdr.jpg)
![青森市/大鰐町/弘前市[東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/4817/7061/9691/jreast-takaramono-01_hdr.jpg)
![沁みる東京おでんのつくりかた[おいしいおでんが食べたい!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/4717/7061/4981/metro276_special_05_hdr.jpg)
![「東京おでんだね」の源太さんに訊く “関東おでん”の世界[おいしいおでんが食べたい!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9417/7061/4450/metro276_special_04_hdr.jpg)
![おでん種を買いに。[おいしいおでんが食べたい!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9017/7061/3751/metro276_special_03_hdr.jpg)