先日、参加していたある会で前の席の方がナッツをくださいました。手を洗えない場面だったので、それを懐紙に載せて両隣の方にお渡しすると、お二人とも「可愛い。この懐紙、もらってもいいですか?」とのこと。透かしが入った一般的なお懐紙だったのですが、興味をもってくださったその言葉に、自分も初めてお懐紙を見たときのときめきを思い出しました。
懐紙とはその名の通り、懐に入れて持ち運べる、小ぶりで二つ折りになった和紙のことを指します。お茶席でお茶菓子を載せる紙、というとピンとくる方が多いのではないでしょうか。茶碗の口を拭うときにもつかいますね。そのほか、貝が砂を噛んでいたときには、口を拭うふりをしてそっとお懐紙に包んだり、食べ終えた魚の骨や皮の上から懐紙を載せて伏せたりということもあります。これらをティッシュですると一気にリアルな感じがでるので、それを覆い隠してくれる懐紙はとっても便利。メモにもなりますし、また、心づけや現金を渡すときにぽち袋がなくても、懐紙に包んで気持ちを届けられます。和紙なので、蛇腹に折った懐紙を水を張ったコップにつけると適度な湿度を保つこともできます。最近は古典文様だけでなく、いろんなタイプの懐紙が出ているので、季節や気分で懐紙を選ぶのも楽しいですね。
懐紙を使う際の注意点をいくつかあげると、二つ折りの輪を自分の方に向けて使うこと。向きにはいつも注意しましょう。そして、2、3枚だけ持ち歩くのではなく、束で持ち歩き、取り分けなどに使うときには、一番上の懐紙を裏返しに折って、外に出ていなかった面を使うこと。とにかくお懐紙は清潔に。汚く見えないことはとっても大切です。バッグに入れて持ち歩くなら、くしゃくしゃにならないように、袱紗(ふくさ)挟みを使うのがおすすめ。ぜひ、お懐紙を暮らしに取り入れてみてくださいね。
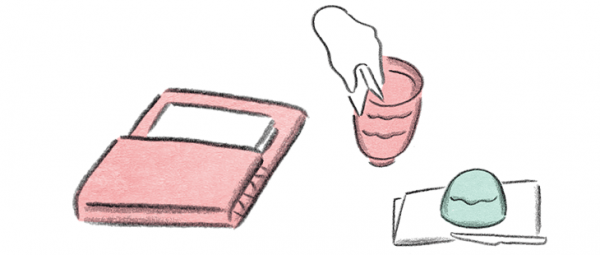
ちより
エッセイスト。元新橋芸者。美しい女性に憧れ続け、日々美人を観察している。主な著書に『捨てれば入る福ふくそうじ』『福ふく恋の兵法』。男女のコミュニケーションについての講演が人気で全国を回る日々


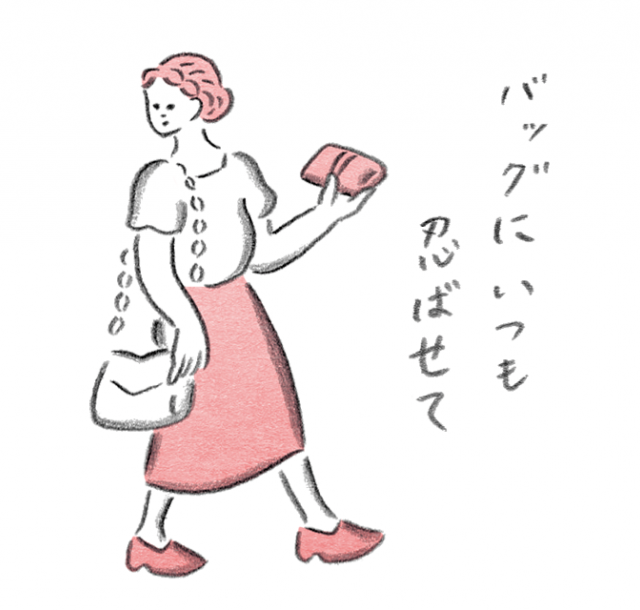

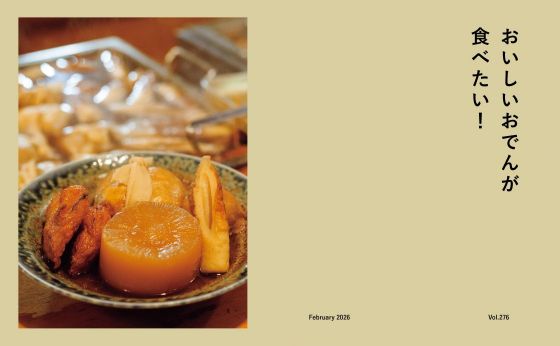

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)
![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)
![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)
![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)