日本三大祭りの一つで、夏の京都の風物詩「祇園祭」の前祭(さきまつり)のハイライトとなる「山鉾巡行」が17日、京都市の中心部で華やかに繰り広げられました。
色鮮やかなタペストリーなどの懸装品(けんそうひん)や豪華な金具で飾られた山鉾は、まさに「動く美術館」。23基の山鉾が祇園囃子を奏でながら都大路をゆっくりと進む様子は、まるで「祇園祭絵図屏風」に描かれた世界が現代に蘇ったかのようです。
朝方に降り始めた雨も不思議なことに午前9時の巡行スタートのころには止みました。沿道に詰めかけた観客の熱気に後押しされるように、音頭方の「エンヤラヤー」の掛け声で先頭の長刀鉾(なぎなたほこ)が四条通烏丸を出発。今年新調した江戸時代の絵師、伊藤若冲の「旭日鳳凰(ほうおう)図」をモチーフにした幕が注目を集めていました。


山鉾巡行の順番は7月2日にくじを引いて決めますが、長刀鉾は毎年先頭を行くことになっており「くじ取らず」と呼ばれます。鉾先に疫病や邪悪を祓う三条小鍛冶宗近作の大長刀を付けていたことからこの名がつきました。生稚児と2人の禿(かむろ)を乗せる唯一の鉾です。
四条通麩屋町に差し掛かると、金銀丹青に彩られた鳳凰の冠をかぶり、赤地の錦に金襴をほどこした衣装に身を包んだ長刀鉾の稚児、粂田龍志(りゅうしん)君が、四条通に張られたしめ縄を見事な太刀さばきで切り落とし、沿道からは大きな拍手と歓声が沸き起こりました。

華麗な稚児舞を披露する長刀鉾の稚児、粂田龍志君(写真・田中幸美)
交差点では山鉾の進行方向を90度転換する「辻回し」が行われ、車輪の下に竹を敷き詰めて、山鉾の引き手の男性らが掛け声に合わせて勢い良く縄を引っぱると、バリバリッと音を立てながら向きを変えました。
沿道には台風の影響で6万5000人にとどまった昨年の約3倍にあたる約19万人(府警調べ)が詰めかけ、四条通は身動きが取れないほどでした。
祇園祭山鉾連合会の岸本吉博理事長は「日本を代表し、世界に知られる祭りになるよう努力しています。こうした文化遺産を維持継承するためのいろいろな人たちの力添えに感謝しています」と話していました。
夕方には八坂神社(京都市東山区)から神輿が四条通の四条御旅所(おたびしょ)に向かう神幸祭の神輿渡御(みこしとぎょ)もあり、威勢の良いかけ声が響いていました。
後祭の10基による巡行は24日に行われます。



囃子方は巡行の間中、休むことなくお囃子を奏でます。写真は鶏鉾の囃子方(写真・田中幸美)

カマキリのからくり人形がのっていることで人気の蟷螂山(写真・田中幸美)

綾傘鉾は、辻などに差し掛かると赤熊(しゃぐま)をかぶった棒振り囃子が踊りを披露します(写真・田中幸美)

至宝の前懸「イサクに水を供するリベカ」を飾って巡行に臨む函谷鉾(写真・田中幸美)

道幅の狭い新町通を進んで町内に帰る月鉾。山鉾との距離がグッと近くなるのが魅力です(写真・田中幸美)

新町通を行く綾傘鉾の一行(写真・田中幸美)





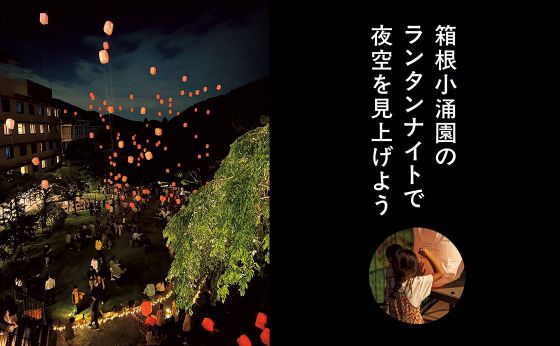

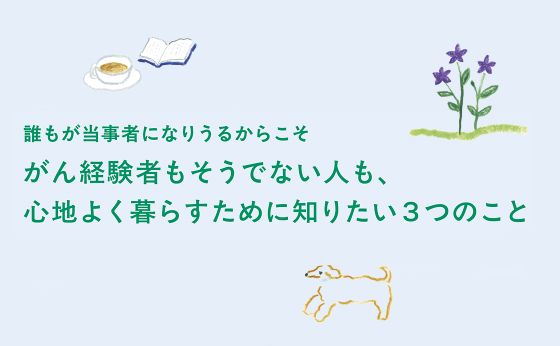
![ハラハラしない投資って?[FP流!お金のヒント帳]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5617/5998/3274/metro272_fp-office_hdr.jpg)
![今月の旬:栗[令和の日本風土記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/5998/2678/metro272_seasonalfoodintokyo_hdr.jpg)