私は、大学院博士課程の3年生です。あと1年、論文と格闘してうまくいけば修了できますが、さすがに博士課程は厳しく、論文の査読(複数の教授が審査する)などは“シゴキ”に近く、これは“愛のむち”なのだと自分を納得させています。
より良い論文にするための通過儀礼のようなものかもしれませんが、この厳しさは体験した人にしか分からないでしょう。
コーヒーが好きで、1990年に世田谷区船橋で堀口珈琲を創業しましたが、現在は実務から離れ、大学の食品科学の研究室で女子大生ら(栄養学科で女子が多い)に囲まれ、コーヒー研究についてしています。シニア割引(年来を推測してください)も学割も両方使えますので便利ですぞ!
近年、大学では社会人枠を設け、ちゃんと勉強しようと考えている人を受け入れています。研究したい、学位を取るためなど目的はさまざまです。
修士課程2年生のSちゃんは、大学を卒業し6年間働いて、大学院の2年分の授業料と、ぎりぎりの生活費をためて入学してきました。いやいや、すごいガッツですね。一生懸命、節約してきたんだな、と尊敬してしまいました。
私は、コーヒー業界では、スペシャルティコーヒーの黎明期から先端を走り、世界中の生産国を巡りました。100店のビーンズショップ(生豆を焙煎し販売する業態)の開店支援をし、数々のセミナーも開催し、1万人以上の受講生に教えてきました。

これまで、10冊の実用書を出版(「珈琲の教科書」新星出版社[2008年]はロングセラーです)。でも、コーヒーは収穫から抽出まで科学的には曖昧なことが多く、検証してみたいと「崇高かつ馬鹿なこと」を考えてしまい大学院に入りました。
基礎もないのに、理化学的な分析を行おうというのですから無謀ですよね。B型の文系タイプで、感性で世の中を渡ってきましたので、さすがにギャップも大きく、多くのストレスを抱え、いまだに悪戦苦闘しています。
当たり前のことですが、ゼミや学会発表のパワポも自分で作らねばならず(これまでは社員に作ってもらっていました)、統計解析なども一から始め、脳ミソはパニック。学術的な文章は、結果という事実のみから考察しなければならず、従来の文章とは異なり「~と推察される」などの表現に慣れるには時間がかかりました。学術の世界では、まだよちよち歩きの新米です。
しかし、今は充電中とでもいうのでしょうか?「自分でもどこに向っているのか」、「この先何ができるのか」、予測できない状態です。
今後1年で、自分にどんな変化が起きるのか、分かりませんが、若干のプライベートも混ぜながらコーヒーについて、お伝えしていこうと思います。
まずは、そもそもコーヒーの風味(香り+5味+コク)って何? つまりは、コーヒーのおいしさって何? から。
この質問に答えることは意外に難しく、すべてはこの問いからスタートします。話しは多岐に渡りますが、お付き合いいただければ幸いです。
堀口珈琲 www.kohikobo.co.jp





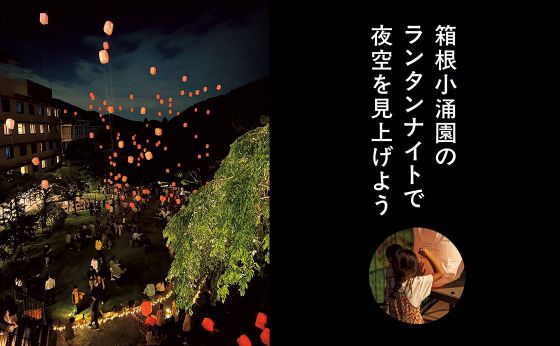

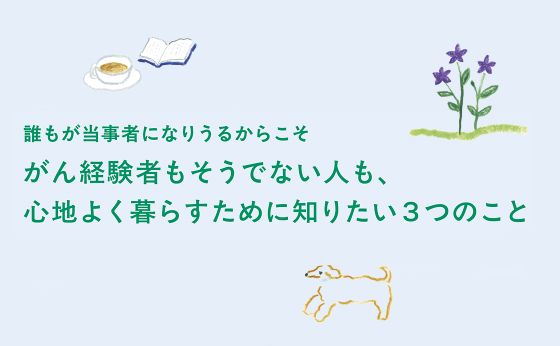
![ハラハラしない投資って?[FP流!お金のヒント帳]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5617/5998/3274/metro272_fp-office_hdr.jpg)
![今月の旬:栗[令和の日本風土記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/5998/2678/metro272_seasonalfoodintokyo_hdr.jpg)