海を越え、大自然でパワーチャージする伊豆大島の旅
~東海汽船の船旅~
Vol.1 夜行船で行く、神宿る“御神火”の島へ(後編)
都心から南へ約120kmの太平洋に位置する伊豆諸島の玄関口・
島の人たちは、独自の暮らしを営み、文化や産業を発展させてきた
地球の記録を垣間見られる景色
伊豆大島の岡田港に到着後、レンタカーを借りて、岡田から西まわりに南部の港町・波浮へ移動する。その途中、大島一周道路の山側に、巨大な縞模様の「地層大切断面」が約630mにわたって出現する。島ではその見た目からバームクーヘンという愛称で呼ばれている。過去約1万8000年の間に幾度となく噴火し、そのたびに噴出物が積もってできた地層で、地球の記録といえるジオサイトの一つだ。
波浮は、川端康成の小説『伊豆の踊り子』の舞台となったレトロな街並みが印象的で、島内随一の“昭和っぽさ”を感じられる場所だ。ここも、火山島らしい成り立ちの物語がある。
かつて、波浮港は火山の火口湖だったが、元禄16(1703)年の地震による大津波で、海とつながった。寛政12(1800)年に、江戸の商人・秋廣平六が一大工事を行って現在の姿になった。それから風待ちの良港として栄え、多くの文化人も執筆などを目的に訪れるようになった。



世界で唯一無二の自然に、地球を感じる
三原山は古くから「御神火」と呼ばれて、人々に崇敬されてきた。三原山展望台から真正面に三原山を望むと、頂から麓に向かって5つの黒い筋が見える。1986年の噴火の際に、火口から溢れ出た溶岩流が通った跡だ。麓に広がる大地は、約1700年前の噴火によって陥没したカルデラ地形で、一帯はごつごつした溶岩やその隙間に根を張る低木、金色のススキ野原が見られる。
三原山は1777年に発生した安永の大噴火で、カルデラの中に形成された新しい山だ。一夜にして異なる地形に姿を変える噴火は、たしかに恐れを抱くが、目前の景色は地球が見せてくれる一期一会のものであるとすれば、尊く思える。
よく、「月面みたい」「惑星のよう」と喩えられる裏砂漠は、三原山の東側に広がる。私も初めて行った時は、こんな異世界じみた自然が東京にあるのかと驚いた。
延々と続く黒いスコリアの大地と広大な空で構成された世界を歩く。ザクッ、ザクッ、ザクッと音を鳴らしながら大地を歩くのは不思議な気分だ。裏砂漠は1986年の噴火前までは細かい砂のような噴出物に覆われ、1931年にはラクダやロバが導入されて「砂漠観光」が行われていたという。空と大地を区分するなだらかな稜線を目で辿っていると、遠近感が掴めなくなり、自分も自然に溶け込んでしまうような気がした。
宿泊は、三原山展望台に近い大島温泉ホテルだ。伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局の臼井里佳さんは、「大島温泉ホテルから三原山に続くルートを歩いてほしい。噴火によって焼失した植物が、少しずつ再生する植生遷移の過程を観察できる」と話していたので、次回の目的にしたい。
満天の星を眺めながら温泉に浸かり、旅の夜の静寂をしみじみと味わった。


伊豆大島へのアクセス:
竹芝桟橋や横浜大さん橋、熱海などから東海汽船の大型客船「さるびあ丸」とジェットフォイル「セブンアイランド」4隻が運航している。
詳細は東海汽船のHPまで https://www.tokaikisen.co.jp/
文:小林希
プロフィール:旅作家・元編集者。著書に『週末島旅』など。日本の離島130以上をめぐる。現在、日本旅客船協会の船旅アンバサダー。産経新聞などで連載中

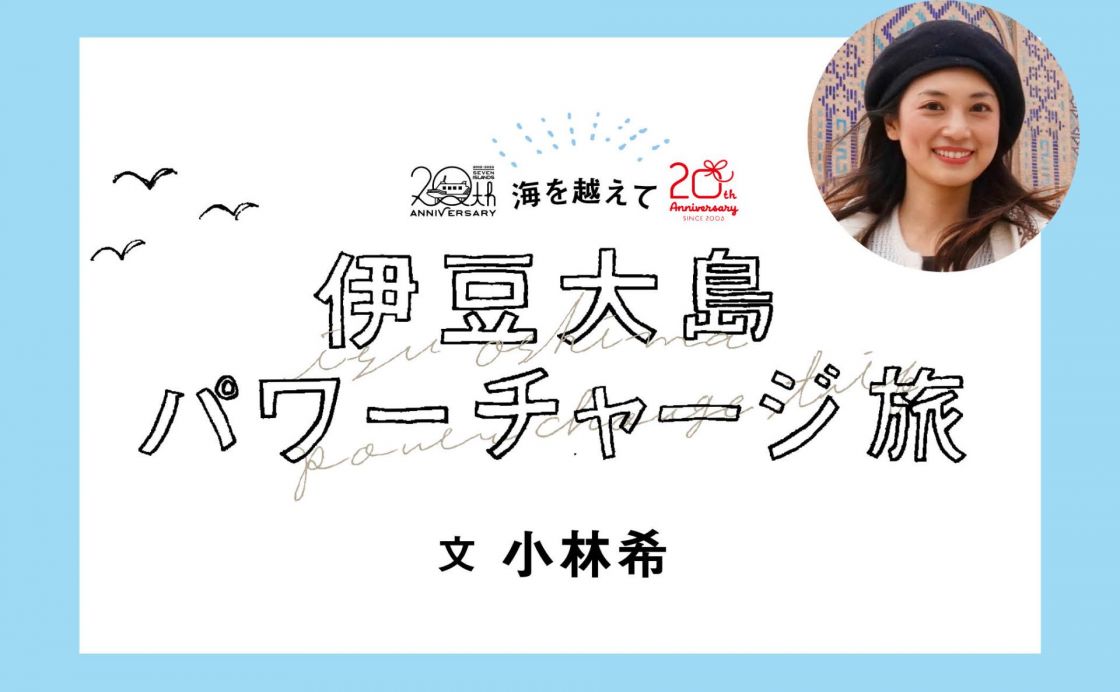


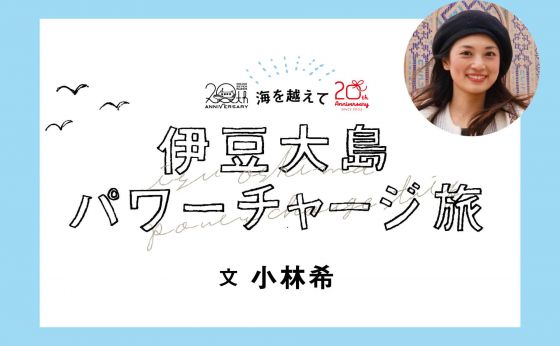

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)
![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)
![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)
![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)
![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)