消費税増税が家計を圧迫し、老後資金に関して不安が募るニュースが報じられるなど、ますます気になる”お金”のこと。超低金利が続く中、預貯金だけで十分な蓄えを備えられるか疑問に思い、資産運用に興味を持つ人も多いはず。でも、いつかちゃんと学ぼうと思っても仕事やプライベートで忙しいし、なにより難しそうでなかなか手を付けられない。
そんな悩みに応えるため、J-REIT(不動産投資信託)を中心に資産運用を学べる女性限定のセミナー「J-REIT女子会」が9月27日(金)、日本橋兜町で開かれました。
会場は東京証券取引所近くの「CAFE SALVADOR BUSINESS SALON」。普段は近隣で働く証券会社員も利用する落ち着いた雰囲気のカフェですが、この日はおいしそうなスイーツとウエルカムドリンクのシャンパンが並び、「女子会」らしい華やかな雰囲気に。開始時間の18:30が近づくにつれ、仕事帰りの20~40代を中心とした約30人が続々と集まりました。


セミナーには講師としてアイビー総研投資情報室の関大介さんのほか、投資法人で投資家向け広報を行うIR担当の女性3人が参加。最初は、講師が初心者にも分かるようJ-REITを丁寧に解説してくれました。
「不動産への投資といっても、実際にマンションを買うのと大きく違います」と関さん。マンションは多額の頭金やローンなど”一生に一度の買い物”というイメージがありますが、REITは「投資信託」とあるように金融商品です。多くの投資家から資金を集めて運用するので、少額から始められるし、不動産管理などの煩わしさもありません。
また、金融商品といっても、配当にあたる「分配金」は投資先の不動産の賃貸料収入などを原資としているので比較的安定しているのも特徴です。もちろん、価格変動のリスクはありますが、マンションは購入物件の選択の影響を直接受けるのに対し、REITはプロが投資先を選ぶうえ、複数の不動産を組み合わせることで分散しています。
少額から、手間や時間もかけずに投資でき、比較的安定した分配金もある―ここまで説明を聞き、参加者も興味津々の様子。関さんは「きちんと仕組みを理解して運用し、リスク分散していきましょう」と呼びかけていました。
では、実際にどんなREITがあるのでしょうか?ここで投資法人3社の現役IR担当者から、運用の特徴などのプレゼンを聞きました。
トップバッターは、不動産を管理・運営し、資産価値を最大化するプロパティマネジメント(PM)業界のトップ企業が運用するザイマックス・リート投資法人の田川優さん。「プロパティマネジメントで、受託物件が国内No.1(PM受諾面積)を獲得した実績もあるザイマックスグループのノウハウが基盤です。オフィスや商業施設に加え、ホテル、住宅など投資先物件の用途の多様性や、首都圏以外にも全国で受託実績を積み重ねてきたのが強みです」。物件用途や対象地域のバラエティが広がれば、景気の浮き沈みにも対応できそうです。
次は、総合不動産会社トーセイが100%出資するトーセイ・リート投資法人の山田紗矢香さん。「1都3県を中心とした”東京経済圏”の中小規模不動産を対象に投資しているのが主な特徴です。住宅、オフィス、商業施設への投資がメーンで、物件を厳選して取得し、着実に規模を拡大してきています。競争力のある物件の見極めや、改修・改装など付加価値を高めるノウハウを持っていることがアピールポイントです」。地域を絞り込み、プロならではの目利きや不動産の価値向上が見込めることが魅力的ですね。

最後は、三井物産がサポートする日本ロジスティクスファンド投資法人の金子智衣さん。「(倉庫など)物流施設に特化しています。高速道路や空港、港湾の近くに立地し、市街地へのアクセスも有利な優良物件や、大規模物件がメーンの投資対象です。賃料収入が基本という点はオフィスや住宅(のREIT)と変わりませんが、インターネット通販市場の拡大に伴う物流業界の成長で、施設需要も見込まれることがポイントです」
全国と東京中心、大規模と中小規模、オフィスと物流…三者三様の特徴を理解し、参加者もそれぞれの関心によって、より深く知りたいと好奇心を刺激されているもようです。
そこでセミナー後半は、3つのグループに分かれて座談会。講師を囲むカジュアルな形式で、参加者からは「リスクの少ない始め方はありますか」「銘柄選びのポイントはありますか」など具体的な質問が次々と飛んでいました。先生のアドバイスや解答に真剣に耳を傾ける姿がどのテーブルでも見受けられ、約1時間40分のセミナーはあっという間に終了の時刻に。

参加者からは「最初はハードルが高いと思ったけど、思っていたよりも始めやすそう。選択肢として考えてみたい」と感想が聞かれました。
誰にでも将来の不安はつきもの。”いざ”という時の備えとして貯蓄のみならず、投資も選択肢の一つになってきています。「怖い」と思うのは、「知らない」から。思い切って一歩踏み出して学んでみれば、新たな可能性が開けるかもしれません。
協力:プロネクサス




![Session6 超低金利時代を生き抜く! 銀行選びのツボ[聞いてハッピー♥マネーサロン]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1615/6257/3972/door.jpg)
![vol.3 L PACK.[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6532/6068/metro274_culture-in-tokyo_hdr.jpg)
![vol.3 雪原に生まれ変われるほど泣いて泣き飽きたころ春がくること[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5617/6532/5798/metro274_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)
![今月の旬:牡蠣[令和の日本風土記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1917/6526/5571/metro274_seasonalfoodintokyo_hdr.jpg)
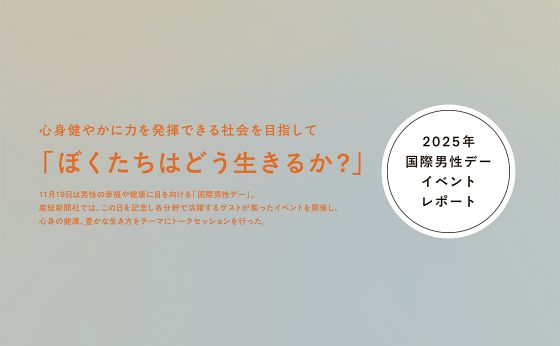

![セルフケアで癒やす[お疲れさま、2025年のわたし!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3917/6525/8293/metro274_special_04_hdr.jpg)