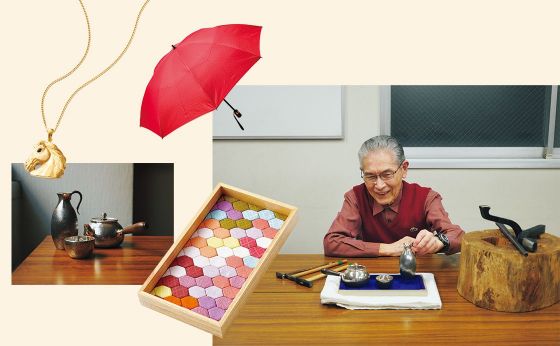明日30日で6月も終わり,今年も半年が過ぎていきますね。この時期になると、境内に大きな茅の輪を設ける神社を見かけます。30日は「夏越の祓(なごしのはらえ)」といい、茅の輪をくぐって、半年間の罪や穢れを祓い、これからの半年の無病息災と厄除けを祈願します。

護王神社(京都市上京区)の茅の輪
京都ではこの日、半年の穢れを祓う和菓子「水無月」(みなづき)を食べる習慣があります。最近では東京の和菓子店でも見かけるようになりました。白い外郎(ういろう)生地にふっくらと炊いた小豆を乗せた三角形のお菓子です。小豆は魔よけの意味があり、三角形は暑気払いの氷を表しているといわれています。
京都のお隣の滋賀でも水無月を食べる習慣が一部にあるそうです。1865年創業の「しろ平老舗」(滋賀県愛荘町)は、もともと外郎や酒饅頭の提供から始まり、普段は「宿場外郎」と称して取り扱いをしていますが、この時期になると水無月に切り替えます。5代目の岩佐昇さんによると、シンプルな白い外郎に加え、黒糖や抹茶を練り込んだものも人気だそうです。

「彩雲堂」(松江市)の水無月

「しろ平老舗」(滋賀県愛荘町)の水無月
そして翌7月1日(旧暦の6月1日)、かつて宮中では氷を保存する氷室(ひむろ)から氷を取り寄せ、暑さをしのぐ行事が行われていました。金沢ではこの日、加賀藩前田家が江戸の将軍家へ氷を献上する「氷室開き」が行われていました。その際に、無病息災を願って食べられていたのが氷室饅頭です。
この時期、金沢のあらゆる和菓子屋はいっせいに氷室饅頭を作りはじめ、さながら「氷室饅頭戦争」の様相となるそうです。石川県白山市の「雅風堂」3代目、安田卓司さんによると「企業さんも取引先に一斉に氷室饅頭を配ったりします。氷室饅頭がなぜ金沢地域だけに広がるのかはまったくわかりません」といいます。

「雅風堂」(石川県白山市)の氷室饅頭
30日は水無月、1日には氷室饅頭。和菓子に込められた歳時記は、その時々の行事に合わせた古き良き日本の習慣を思い出す手がかりとなります。





![セルフケアで癒やす[お疲れさま、2025年のわたし!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3917/6525/8293/metro274_special_04_hdr.jpg)
![ご褒美体験でねぎらう[お疲れさま、2025年のわたし!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6417/6525/7380/metro274_special_03_hdr.jpg)
![薬膳で身体をいたわる[お疲れさま、2025年のわたし!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5917/6525/4730/metro274_special_02_hdr.jpg)
![心地よく部屋を整える[お疲れさま、2025年のわたし!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1817/6525/3263/metro274_special_01_hdr.jpg)