海を越え、大自然でパワーチャージする伊豆大島の旅
~東海汽船の船旅~
Vol.2 島を彩るツバキの楽園へ(前編)
海を越えるとたどり着く別天地、伊豆大島。都心から南へ約120kmの太平洋に位置する伊豆諸島の玄関口となる島だ。数万年前の海底噴火で誕生し、その後も噴火を繰り返して成長した火山島である。
伊豆大島は約300万本のヤブツバキが自生し、冬から初春にかけて色鮮やかなツバキが島を彩る。毎年1月下旬から3月下旬まで椿まつりが開催されている。
船に乗って、非日常の世界へ飛び出そう!

世界に誇るツバキの楽園、夏や秋に咲く新種も
伊豆大島は、「東の大島、西の五島」と称されるツバキの名産地。温暖多雨な気候と水捌けの良い火山の土壌はツバキが生きる環境に適している。島では、5000年〜8000年前の地層には、葉の化石も見つかっている。
島の人々は、昔からツバキを防風林として重宝し、種から搾油して食料や化粧品など生活に利用してきた。昭和初期には島の椿油が国内でブームとなり、一大産業にもなった。現在は、“ツバキの鑑賞”が注目されている。
「日本一の“早咲きツバキ”が見られる島にしたい」と夢を語るのは、椿花ガーデンの山下隆さん。たった一人で、40年かけて花の咲き誇るガーデンを作り上げ、管理している。園内の富士見の丘は、島内屈指のパノラマスポットで、ツバキと富士山のコラボレーションを見ることができる。
園内では、通常、春はオオシマザクラ、初夏はアジサイ、冬から初春にかけてツバキが見られるのだが、なんと山下さんが6年前に授粉させたツバキが、今年の“夏”に咲いた。中国の夏に咲く種の「アザレアツバキ」と五島列島の名産ツバキ「玉の浦」を掛け合わせるのに成功したのだ。
きっかけは、「秋、紅葉の代わりにツバキを見に島へ来てくれないか」と思い、山下さん自ら山の中を歩き回って、ついに早咲きツバキという“変異種”を探し当てたのが始まり。その後、根気強く授粉を続けて、現在では秋から冬の期間に花が開く「早咲き」のツバキが園内に100種以上もあるという。
「夏と秋も咲けば、正真正銘のツバキの島。40年という歳月で、僕がイメージする花園にようやくなってきたと思う。しっかりと土台を築いたものは、美しいでしょう?」と微笑む山下さんに、島の宝はまさしく“人”であると確信した。


平成28年、伊豆大島の大島公園、大島高校、椿花ガーデンが「国際優秀つばき園」に認定された。ツバキは観光においても希望の光となっている。
東海汽船では、椿まつりにあわせたツアーも多く企画している。
伊豆大島へのアクセス:
竹芝桟橋や横浜大さん橋、熱海などから東海汽船の大型客船「さるびあ丸」とジェットフォイル「セブンアイランド」4隻が運航している。
詳細は東海汽船のHPまで https://www.tokaikisen.co.jp/
文:小林希
プロフィール:旅作家・元編集者。著書に『週末島旅』など。日本の離島130以上をめぐる。現在、日本旅客船協会の船旅アンバサダー。産経新聞などで連載中。

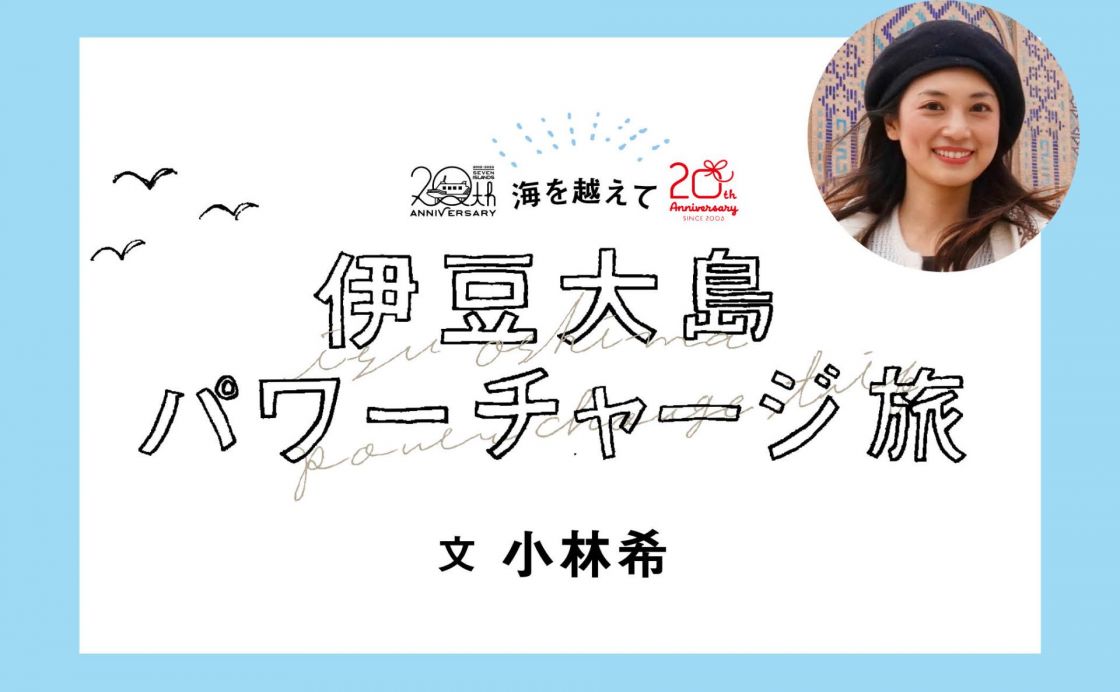


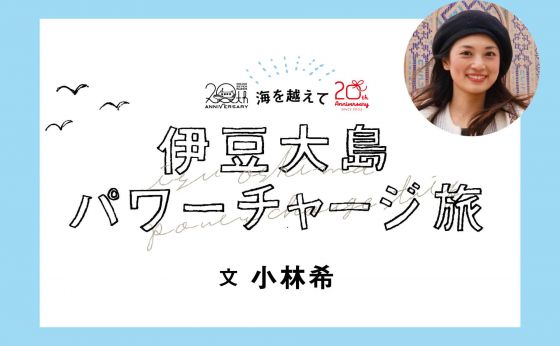

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)
![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)
![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)
![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)
![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)