9月1日で、関東大震災の発生から丸100年。いつ、どんな災害が起こるかは誰にもわからないだけに、「もしも」のことを考え、備えをしていくことは重要だ。この特集では、防災心理学者の矢守克也先生と総合プロフェッショナルファームのリッジラインズを迎えて、防災の考え方やヒントを一緒に探っていく。日頃の備えと心がけで、行動は大きく変わってくるはず。いまから、もしものための準備を進めていこう。
写真右)京都大学防災研究所 教授
矢守克也さん
1988年、大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学。奈良大学社会学部助教授などを経て、現在は京都大学防災研究所教授。主な著書に『巨大災害のリスク・コミュニケーション』(ミネルヴァ書房)、編著に『被災地デイズ』(弘文堂)。
写真中)リッジラインズ D&I推進室 Manager
今井智香さん
2004年、大手SIベンダーに入社後、クライアント企業の業務定着や意識変革活動に従事。「個人」に着目した組織の成長に関わるプロジェクトの実績を多く持ち、現在はリッジラインズにてDXに特化した企業のブランディングやD&Iの推進を担当している。
写真左)リッジラインズ Director、防災士
川嶋孝宣さん
帝人や日本IBMなどを経て2022年4月より現職。ヘルスケア領域を中心に国や自治体、企業との連携事業などに携わり、東日本大震災時には震災復興プロジェクトを発足。各業界で「健康・ヘルスケア」による価値の創出を目指し、企業をサポートしている。
これからに備えていくために、
昔といまの違いを知ることが大切。
今井:「正解のない問いを考える」という意味で、防災の考え方とコンサルティングには通ずる部分があるなと感じていて。今回お話を伺えることを楽しみにしていました。関東大震災や豪雨による河川の氾濫など、日本はこれまでさまざまな災害を経験してきましたが、令和における「防災」としては、どんな備えを考えておくべきでしょうか?
矢守:自然災害は、時代にかかわらず繰り返しやってくるものです。とはいえ、関東大震災が発生した100年前といまでは、社会のあり方が大きく違うため、備えについては慎重に考える必要があります。高齢化は遥かに進んでいるし、電気や交通といったインフラや私たちの生活も、昔とはまるで異なりますよね。社会活動の中心地であり人口の多い東京で電気が止まることの影響や、高齢者がおよそ4人に1人いる現代社会で災害が起こることのリスクなど、まずは昔との違いを把握することが大切だと思っています。
今井:3.11(東日本大震災)のときは首都圏の電車が止まり、駅周辺は移動の手段を失った人であふれました。当時、私は東京のオフィスにいたのですが、ビル内のエレベーターが止まり、みんなで慌てて1階に下りたんです。でも振り返ると、ビルは耐震設計でしたので、その場にとどまるほうが安全だった。経験したことがないと、大人でもわからなくなってしまうものなんだなと。
矢守:まさにその通りです。一方で、これから起こるかもしれない災害とまったく同じ事例が過去にあるわけがないので、「この災害を勉強しておけば完全な対策になる」というものはありません。ただ、次に起こるかもしれない災害のいくつかの状況を予想できる事例はたくさんあります。「大規模な停電が起こったら、3.11のときのように帰宅困難者が出るだろう」「阪神・淡路大震災のように、大地震が起きたら木造の建物が倒れて火事になるかもしれない」など、過去の事例からピースをつなぎ合わせて、次の災害の全貌を想像しておくことが大切です。
多様な人が行き交う現代こそ、
手を取り合うチームづくりが鍵。
川嶋:災害時にどこにいるかによって、人の動線も大きく変わりますよね。東日本大震災時、土地勘のない出張先で被災した人が、避難先や動線を想像できずに1カ所に集まって混乱してしまった、という話を聞いたことがあります。東京には、似たような局面がもっとある気がしていて。ビジネスで来ている人や外国人旅行客など、“たまたま来ている人”の受け入れ体制も課題ですよね。
今井:たとえば旅行中に東京で被災したとして、品川方面や東京方面などに避難しろと言われても、自分がいる場所からどちらに行けばいいのかわからないですよね。
矢守:停電して周辺が真っ暗だったら、もっと厳しくなりますね。そうしたときに、情報を持っている方が手を差し伸べてあげたり、たとえばその場に日本語がわからない外国人がいてパニックになっていたら、英語が話せる方がいないか周囲に呼びかけたりしたいものです。たとえ他人同士であっても、こうした状況だからこそ協力し合いたいですね。
今井:ジェンダーの視点で考えてみると、たとえば女性は、お手洗いや着替えなど人目に触れたくない場面が多いと思います。災害時、こうした同じ悩みを抱えた人同士で協力し合ったり、女性に限らず不特定多数の人が集まる場で声をかけ合って、最善の策を探ることも大切だと思いました。
矢守:そうですね。避難所で誰とも話さず、全員がそれぞれスマートフォンを使って同じニュースを見ている光景はすごく不思議です。であれば、1台のスマホで情報収集をしてみんなに伝えてあげて、ほかの人は次の利用場面に備えて電源を切ったほうがいい。難局を乗り切るための即席のチームづくりが鍵になります。適切な例かはわかりませんが、W杯で勝利した日のスクランブル交差点にいるDJポリスは、それに近い気がしています。彼らは指示や命令だけでなく、チームづくりをする努力もしているんです。「日本代表だけではなく、私たちもワンチームです。みなさんが安全に帰宅できるよう、協力し合って駅まで楽しく歩きましょう」と。災害時も、みんなで協力し合って前を向けるようなチームづくりが求められます。
川嶋:日頃からさまざまな場面を想像して、周囲とコミュニケーションをとり、災害を自身でも乗り切る力を養っておきたいですね。
リッジラインズとは?
“未来を変える、変革を創る。”をミッションに掲げ、企業が抱える課題に対して、その戦略の立案から実行までを支援して解決へと導く、総合プロフェッショナルファーム。社会に新しい価値を提供していくことを目指し、社を挙げてD&Iの推進に力を入れている。

![想像しよう、もしものこと[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/3916/9405/9869/metro247_special_01_hdr.jpg)
![想像しよう、もしものこと[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/3916/9405/9869/metro247_special_01_hdr.jpg)

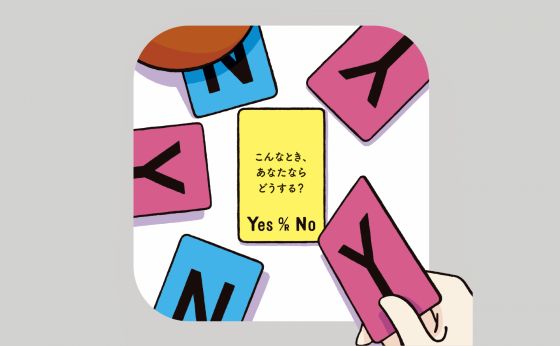
![vol.5 上田優紀(写真家)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1217/7061/6142/metro276_culture-in-tokyo_hdr.jpg)
![vol.5 来世ごと賭けた勝負に負けたからこんなになにもない風の星[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3517/7061/5892/metro276_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)
![JR東日本で東北を旅しよう![東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7217/7077/6695/metro276_jreast-takaramono-05_hdr.jpg)
![《目的別で見つける東北の宝もの》学ぶ宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3017/7077/5670/metro276_jreast-takaramono-04_hdr.jpg)
![《目的別で見つける東北の宝もの》癒やされる宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5217/7077/4672/metro276_jreast-takaramono-03_hdr.jpg)
![《目的別で見つける東北の宝もの》食べる宝もの6選[東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6017/7062/3201/metro276_jreast-takaramono-02_hdr.jpg)