昨年12月、うれしいニュースが飛び込んできた。日本の「伝統的酒造り」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されたのだ。日本が古くから積み重ねてきた、麹を扱う知識と技術が、あらためて世界に認められた瞬間だった。そして日本酒は、その伝統的酒造りの代表格。長い歴史の最前線では、いまどんな酒が生まれているのか? おいしい日本酒を探しに、出かけてみよう。
令和の日本酒事情
《Interview》
なぜソムリエが、日本酒を推してるの?

横浜君嶋屋 代表取締役
君嶋哲至
きみじま さとし。日本酒、焼酎、泡盛、ワインなどの販売・卸売を手掛ける「横浜君嶋屋」の4代目。日本ソムリエ協会副会長。IWC SAKE部門・パネルチェア、SSI名誉唎酒師酒匠など、お酒に精通するスペシャリスト。講師としても活躍する。
日本ソムリエ協会が、資格試験「SAKE DIPLOMA※」をスタートしたのは2017年のこと。東京オリンピックを前に、日本のソムリエが海外からのお客様を國酒(こくしゅ:日本のお酒)で、もてなすことを目指したのがその始まりだ。日本ソムリエ協会の田崎真也会長の“日本のものを、國酒を大切にしなくてはいけない”という使命感もあった。その当時から、協会の副会長であった君嶋哲至さんは「香り、味わい、品種、土壌など、ワインと同じように、日本酒も分析して伝えていくことで、ソムリエたちがより深く理解できるだろう」と考えた。樹木であるブドウより、一年草である米のほうが、つくられる酒にテロワール(作物を取り巻く自然環境)が色濃く映し出されるとも思ったという。つくり手にも「米」を徹底的に研究して、テロワールを生かしたおいしい酒を醸す人たちが登場する。つくりを工夫した新しいスタイルや、トラディショナルなつくりにこだわるものなど多彩な日本酒がそろい、自由に選べる時代になった。
※現在、資格保有者は6803名(2023年累計)
日本酒を楽しむために
知っておきたいこと。
飲むための知識があれば、よりお酒を楽しめる。まず知っておきたいのが飲む温度だ。「たとえば冷たいお酒。マイナス5℃まで冷やした方がおいしいお酒はけっこう多い。とろみのようなものを感じつつ、おいしく飲める。そしてお酒の特徴が感じられて一番おいしいのが常温。常温というのはボルドーの赤ワインを飲む温度で15℃、お酒がおいしさを発揮する。あとは本醸造だったら熱燗(50℃)。これは食中酒として無敵。トラディショナルなつくりの純米大吟醸のぬる燗(40℃)もおいしい」。君嶋さんのおいしいの定義は「もう一杯飲みたくなる」。そのために、酒器もいろいろ使い分ける。洗練されたお酒は平杯(ひらはい)、ガツンと楽しみたいお酒はぐい呑み、山田錦なら大きめのグラスといった具合に。
そして日本酒は、食べ物と合わせて楽しむものだという。食べながら飲む楽しさを感じる、そのためにお酒と料理を合わせていくソムリエ的な発想は欠かせない。「家庭料理には、普通のお酒がいい。本醸造の熱燗でもいい。選び抜いた食材で料理人が手間暇かけてつくった料理には、純米大吟醸のぬる燗を合わせる。料理とお酒は、格と格、洗練と洗練といった合わせ方が大事」。これはなかなかハイレベルだ。一方で「たとえば、日本酒はチーズやクリームなどの乳製品と相性がいい。パフェと日本酒を合わせて提案する店があるくらい。生クリームのケーキにも合う。チーズにはどんな日本酒も合う」。チーズと一緒に試してみると、じつにおいしい! おいしい日本酒の入り口に立った気がした。「日本酒はワインとも双璧になりうる」と君嶋さんはいう。

![令和の日本酒事情[おいしい日本酒]](https://images.metropolitana.tokyo/9917/3629/5422/metro263_special_01_hdr.jpg)
![令和の日本酒事情[おいしい日本酒]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/9917/3629/5422/metro263_special_01_hdr.jpg)

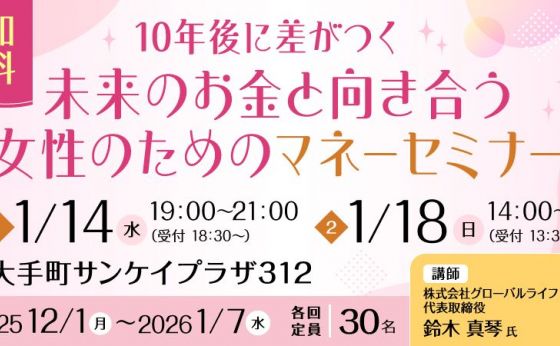
![利用している取り組み「副業制度」[働くも暮らすも〝心地よい〟ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3917/6283/8872/metro273_worklifeintokyo_hdr.jpg)
![トレーニングが自信をくれる(体力の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1617/6283/8621/metro273_yuramekuhikari_hdr.jpg)
![東京メトロ[副都心線]第2回 雑司が谷[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8117/6276/0414/metro273_tokyo-pocket_hdr.jpg)
![vol.2 イザベル・ユペール(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/4217/6275/7603/metro273_culture-in-tokyo_hdr.jpg)
![vol.2 引きで見れば映画のような橋をゆく一人称のからだひとつで[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7417/6275/4083/metro273_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)