ブームの震源地。ホラー小説『近畿地方のある場所について』はどう生まれ、なぜこれほどまでに読まれているのか。著者の背筋さんに話を聞いた。
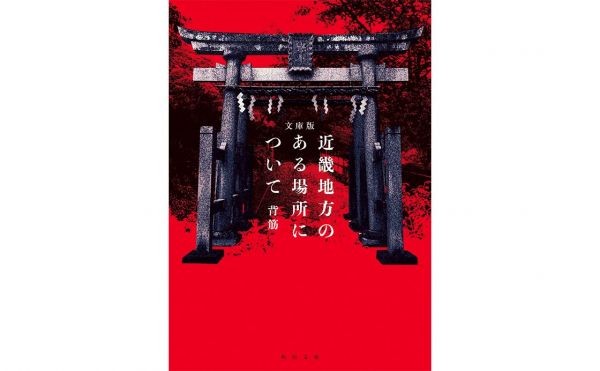
文庫版 『近畿地方のある場所について』
背筋 著/880円/角川文庫
「情報をお持ちの方はご連絡ください」。そんな一文のあと、雑誌記事やネットの書き込み、インタビューのテープ起こしといった多彩なフォーマットの資料の断片で、不気味な事象がつづられていき、それはやがてひとつの大きな真相につながる…。近年のモキュメンタリー・ホラーブームの代名詞とも言える小説の文庫版は、単行本から主人公を変え、内容も異なっている。
背筋
せすじ 作家。2023年に小説投稿サイト「カクヨム」にて『近畿地方のある場所について』を発表し後に単行本化。2024年に『穢れた聖地巡礼について』(KADOKAWA)、 『口に関するアンケート』(ポプラ社)を発表する。
「こんなに読んでいただけるとは、
世も末だなと思っています(笑)」
70万部超えの大ヒット小説は
どのように生まれたのか?
違法サイトの不気味なコメントにまつわる実話怪談。とある行方不明事件にせまった雑誌記事。学生が参加する林間学校で起きた不可思議な事件のルポ…。
小説『近畿地方のある場所について』には、“近畿地方のある場所”に関する雑多な資料が並んでいる。その断片的な情報は、物語の進行とともにじわじわとパッチワークのようにつながり、最終的にはゾッとする結末が浮かび上がってくる。
2023年の1月から4月にかけて、小説投稿サイト「カクヨム」に投稿されたこの作品は、SNSで「これ、実話なのでは?」と話題となり、同年8月には単行本化。現在では、70万部を超えるベストセラーとなっている。今月には、『ノロイ』などで知られる白石晃士監督による映画も公開された。
作者は、当時無名だった背筋さんだ。当初はあくまで趣味の短編で、長編にするつもりはなかったという。
「とにかく短編の怪談を書きたかったんです。最初から断片的なものをつなげていて、長編を書こうとは思っていませんでした。ただ、何篇か書いて掲載しているうちに『このままだとネタ切れするな』と感じて。そこで、もともと好きだったファウンド・フッテージ(※)系のホラー映画のように、『ネット掲示板で配信者を追う書き込み』や都市伝説的な『赤い女の話』なども入れ、さらにその断片的なものを貫く軸となる物語もつくり、ひとつの物語につながるように整えていきました。反響の大きさに、こんなにホラー好きな方が多かったのかと正直驚きました。世も末だなぁ、と(笑)」
そもそも筋金入りのホラー好き。幼少期に触れた『ゲゲゲの鬼太郎』に始まり、『学校の怪談』などもむさぼるように読んだ。またテレビの怪奇モノやホラー雑誌、ネットの掲示板に誰かが書き込んだ怪談も好みだったという。
「『学校の怪談』は民俗学者の常光徹さんが子どもたちに怖い噂話をヒアリングして記したものなんです。だから決してわかりやすく脚色されすぎてもなく、いびつともいえる話も多い。それが良かった。クリアにわかりすぎないところに得体の知れない怖さがありました」
これら過去のホラーコンテンツに触発されて生み出された「ラブレターのようなもの」が、本作だ。インスパイアされて意識している表現もあるという。それが“余白”を残すことだ。
※ 偶然見つかった資料や未編集映像という設定の素材を使用しながらストーリーをすすめる手法
怖さを緻密に設計し、
生み出される面白さ
“髪の長い女性が、歯をむき出して笑っていた”。
たとえばそんな描写をする際、背筋さんは「髪の長さがどれほどだったか」 「口角をどれぐらい上げていたか」などのディテールは、あえて書きすぎないようにしているという。
「読み手一人ひとりに、『何となく怖い画』を思い浮かべてほしいからです。黒沢清監督の映画のように、得体の知れない幽霊や怪物のようなものにはあえてピントをあわせない。対象や事象がよくわからない、余白が残っていたほうが、怖さというものは際立つ気がします。けれど、読者にはただ怖がってもらいたいわけではないんです。その奥深くに眠っている、ドラマに面白さを感じてほしい。怖いと同等に、あるいは、それ以上に『面白い』と感じて、誰かに話したくなるような作品にしたいと思っています」
本作の怖さは、緻密に設計されていた。だからこそ、ぐいぐいと先を読み進めたくなる魅力があり、後味の悪い怖さとともに、不思議な爽快感が並走している。
怖くて、面白い。背筋さんのその追求は、ストーリーテリングや文章表現だけにとどまらない。たとえば、本作を単行本化するにあたり、書籍には当たり前のようにある「目次」をつくらなかった。それは、主人公と同じ目線で資料を読む感覚を演出するため。と同時に、誌面のレイアウトは余白を少なくし、昔のホラー雑誌のようなラフな感じをあえてつくった。付録として袋とじも付け、いかがわしさも含んだドキドキ感を盛り上げた。「本当かもしれない」と思わせる工夫が、小説家としてのサービス精神が、あらゆるところに潜んでいる。
「物語だけを読みたいなら、ネットでタダで読めますから。あえて書籍を、さらに文庫を手にとってもらえるなら、単なる読書以上の体験を届けたかった。だから書籍化する際には、違った体験を楽しんでいただきたかったんです」
7月に出版された文庫版も、主人公を変えて、すでに単行本を読んだ読者も再び楽しめるようにした。脚本協力で参加した映画版も、映像表現ならではの物語性が加えられているという。
面白いものをつくりたい、読者を楽しませたい、という作者の情熱。その考え抜かれた怖さと、謎が明らかになったときのカタルシスを『近畿地方のある場所について』で堪能してほしい。暑い夏に背筋が凍る体験を楽しめるはずだ。

![小説『近畿地方のある場所について』(作家 背筋)[怖いが面白い]](https://images.metropolitana.tokyo/3817/5453/1711/metro270_special_02_hdr.jpg)
![小説『近畿地方のある場所について』(作家 背筋)[怖いが面白い]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/3817/5453/1711/metro270_special_02_hdr.jpg)

![利用している取り組み「副業制度」[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2117/6534/0607/metro274_worklifeintokyo_hdr.jpg)
![子どもは可愛い存在か(母性の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9517/6532/6484/metro274_yuramekuhikari_hdr.jpg)
![東京メトロ[有楽町線]第3回 新富町[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9417/6533/9974/metro274_tokyo-pocket_hdr.jpg)
![vol.3 L PACK.[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6532/6068/metro274_culture-in-tokyo_hdr.jpg)
![vol.3 雪原に生まれ変われるほど泣いて泣き飽きたころ春がくること[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5617/6532/5798/metro274_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)
![今月の旬:牡蠣[令和の日本風土記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1917/6526/5571/metro274_seasonalfoodintokyo_hdr.jpg)