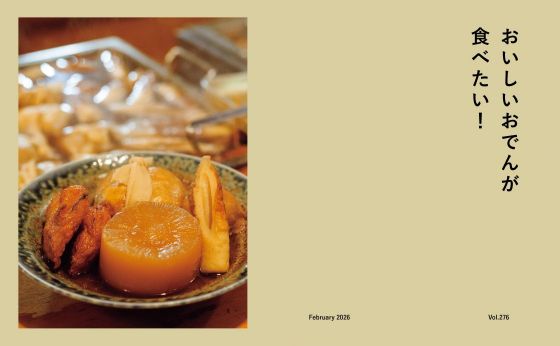誰もが自分らしく生きていくためには、どうすればいいだろう。そんな問いについて考えるDEI体感プログラム「トラハブ」が新たにスタートした。「トラハブ」とはなにか。まずはそこから押さえよう!
日常に潜むアンコンシャスバイアスに気づくことから始めよう!
フェムケアプロジェクトではこれまで、総合プロフェッショナルファームであるRidgelinez(以下、リッジラインズ)とともに、日常はもちろん、災害時にもDEIの観点を取り入れることの重要性についてさまざまな視点で発信してきた。「プロジェクトを推進する過程で、女性だけではなく、多様な背景を持つ人たちの悩みにも寄り添うことが同時に必要だと感じていました。そんなとき、『業界を超えてDEIの輪を広げたい』という思いを持ったリッジラインズの藤田なつみさんと出会って。そこから志を同じくする仲間として、22年の国際女性デーのコラボレーションを契機に、互いに違うカルチャーを持つからこそ生まれる気づきや化学反応の力を体感して。この輪をもっと広げたい!という両者の思いから、トラハブが生まれました」とメトロポリターナ編集長の日下紗代子は語る。
藤田さんには以前、非正規雇用で働いていた職場でのある経験があった。「一緒に働いていた方から、藤田さんは育児中だからあえて非正規を選んでいるんだろうと誤解され、正社員になるチャンスを逃してしまったことがあります。『子育て中だから負担を軽く』という“やさしさ”からくる思い込み(アンコンシャスバイアス)なのですが、一言聞いてくれたらよかったのに…と、モヤモヤしました。同時に、このようなことは自分だけではなくほかの人たちにもたくさん起きているのかもしれないと思い、それぞれが抱えている“モヤモヤ”をオープンに話し合える場づくりが必要だと感じました。トラハブでは、参加者同士が自身の中にある”モヤモヤ”を共有し、対話を通じて、DEIの本質をつかんでいけるような実践的な場になるよう、みんなで考えながら、チャレンジしていきたいです」
協働を重ねるにつれ、リッジラインズの加藤陽さんをはじめとする多様なメンバーも加わった。大学院で義肢装具に関わる最新技術の研究を行っていた加藤さんは、「DEI推進には、テクノロジーの活用が欠かせません。トラハブでは、まず参加者それぞれが ”モヤモヤ”を言語化して共有し、次に”モヤモヤ”が発生する原因を解明。当社の実践知もいかし、カルチャーとテクノロジーという2つの視点で課題解決へと導くアイディアを創造することを目指します。プログラムを通じて、組織でDEIを推進するために必要なことは、個人の”やさしさ”だけではなく、“仕組みで解決する”ことも同時に重要であるということをきっと体感できると思います」とトラハブへの意気込みを教えてくれた。
「いつか『DEI』が当たり前になる日が来ると信じています。でもいまは、積極的に推進していかなければならないほど社会構造が偏ってしまっている。知ることがはじめの一歩です」と藤田さん。日々モヤモヤを感じている方は、ぜひトラハブへの参加を。他者との対話を通じ、自分自身とも向き合うことで、よりよい明日へのヒントにつながるかもしれない。

トラハブ運営の中心メンバーであり、きっかけについて教えてくれた3人。左から加藤陽さん、藤田なつみさん(ともにリッジラインズ)、日下紗代子(メトロポリターナ編集長)。
参加前に知っておこう!
「トラハブ」Q&A
Q1. DEI(DE&I)とは?
Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包括性)の頭文字をとった略称。性別や年齢、国籍などに加え、文化や価値観などが異なる多様な人々が互いに尊重しあい、一人ひとりに合った環境を整え、誰もが公平に能力を十分に発揮できる社会を目指すことを意味している。
Q2. 「トラハブ」とは?
日々、社会や組織の中で感じている心の中の“モヤモヤ”を他者と共有し、その背景にある原因を対話によって解明しようとする試み。フェムケアプロジェクトとリッジラインズが、性別や世代を超えた相互理解を推進するために立ち上げた。
Q3. 「トラハブ」の名前の由来は?
「DEI Transformation HUB」の略称。多様な参加者同士の対話を通じてDEIの体現者を増やすことで、個人から組織へのトランスフォーメーション(変革)を促すことと同時に、同じ思いを持つ人同士をつなげる「ハブ」(中核)になりたいという願いを込めている。
Q4. 今後の展開は?
トラハブでは年間を通じて取り組みを進め、2025年の国際女性デー(3月8日)で成果の発表を目指す。第1回では対話を通じて職場におけるモヤモヤを共有・発散。第2回でモヤモヤ発生の原因をカルチャーの観点で解明し、第3回でテクノロジーを活用した解決策を探っていく。
《EVENT REPORT》
令和の職場のモヤモヤってなんだろう?
〜性別や世代を超えた“対話”を促す「DEI体感プログラム」〜
「トラハブ」第1回の当日は、性別・世代などさまざまなバックグラウンドをもつ約30名が参加。オープニングは「トラハブ」や「DEI」の解説から。続くゲストセッションではSmartHRアクセシビリティスペシャリスト・桝田草一さん、Ridgelinez執行役員Partner・川嶋孝宣さん、産経新聞社メディアビジネス局長・佐々木美恵を迎えて、三者三様の“モヤモヤ”トークを展開。トークテーマは「これまで感じた『わたし』のモヤモヤ」と「自分が属する組織や職場で取り組んでいるモヤモヤ」。職場でのコミュニケーションや個の大切さ、エイジズム、社会的な規範への適応性などに関するそれぞれのモヤモヤの報告に加え、解決策の提案もあった。
ワークショップでは参加者が3人グループになってモヤモヤを発散し、付箋に書き出して開示。性別や世代を超えて共通の悩みを抱えていることに気づく人も多く、大学生の参加者の方は「大人も私たちの世代とあまり変わらない悩みを抱えているのを知って興味深かった」と話した。閉会後の交流会も盛り上がり、「共感する内容が多く、次回もぜひ参加したい」と大好評。次回の新たな展開も、乞うご期待!

ゲストセッションの様子。3名のトーク中には共感するようにうなずく参加者の姿や、笑いに包まれる場面も。

参加者は3名ずつのグループに分かれて、自身が感じるモヤモヤを書き出し、共有しあった。

イベント終了後に行われた交流会にて、ドリンクスポンサーとして提供があった「イヨシコーラ」を片手に、笑顔で談笑する参加者ら。「緊張していたけど参加してよかった」「次回もぜひ参加したい」と、前向きな声が数多く寄せられた。
NEXT EVENT
イベントレポートの詳細はこちらから!
トラハブ第2回はモヤモヤ発生の原因をカルチャーの視点で解明します。
次回からの参加については、下のURLをチェック!
https://metropolitana.tokyo/ja/archive/fcp_torahub_event_report_01

![Ridgelinez × FEM CARE PROJECT「トラハブ」始動![フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/3617/2543/4074/metro259_femtalk_hdr.jpg)
![Ridgelinez × FEM CARE PROJECT「トラハブ」始動![フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/3617/2543/4074/metro259_femtalk_hdr.jpg)