子供の頃、父は私に毎月1冊、本を買ってきてくれました。「次はどんなお話だろう」とワクワクしながら、その日を待ったものです。父のあぐらの上に座り、本を読んでもらうひとときが私は好きでした。
父自身も本をよく読む人でした。「お前も本が好きだな。父さんに似たのかな」と言われるとうれしかったことを覚えています。父は私に、本を読むことの楽しさを教えてくれました。
父は21年前に亡くなりました。それ以降、年に1回の帰省の度に、私は必ず父の本棚を開けるようになりました。変な言い方ですが、父の本棚に呼ばれているような気がしました。並べられている本は変わらないのに、年齢とともに、私の目に映る本が変わっていきます。「こんな本があったの?」「こんなことが書いてあったんだ」と、父が残した本との新たな出合いがあります。
思春期の息子の子育てに悩んだとき、「思春期の子供」の頁(ページ)に栞(しおり)が挟まれた育児書を父の本棚で見つけました。色あせた頁の中に、父が付けたであろう鉛筆の線を見たとき、いつも厳しく毅然(きぜん)とした態度で子供たちに接していた父もまた、私と同じく、子供の成長に戸惑いを感じる親だったのだと驚き、ふっと、肩の力が抜けていきました。帰京する新幹線の中で、その本を読むとき、「大丈夫、大丈夫」と父の声が聴こえてくるような気がしました。
人生の選択を迫られたとき、父の本棚の中の哲学書の言葉が私を励まし、背中を押してくれました。
「父さんだったらどうする?」「何と言うかしら?」。父亡き後も、本を通して、私は父と対話することができました。そして、それらの本は1冊、また1冊と、父の本棚から私の本棚へと移っていきました。今度は、私の子供たちが手にしていくのでしょうか。
親から子へと残すものはそれぞれです。私にとって、父の本は何物にも代えられない大切な財産です。
父が読んだ本を手にするとき、読み込まれた頁の紙の柔らかさや色や匂い、本全体から醸し出す雰囲気から、私は父を身近に感じることができます。それは、タブレット端末の中で出合う本とは一味違う、本が持つ力なのかもしれません。
昨年の帰省では、東洋医学の本を見つけました。「父さん、ここ効くわぁ」と、こっそりつぶやきながら足裏のツボをもんでいます。今はまだ手にしていない歴史小説全集を開くのはいつか、自分でも楽しみに待っています。父の本棚は、今も私に多くのことを教えてくれるのです。(国立音楽大教授 林浩子)




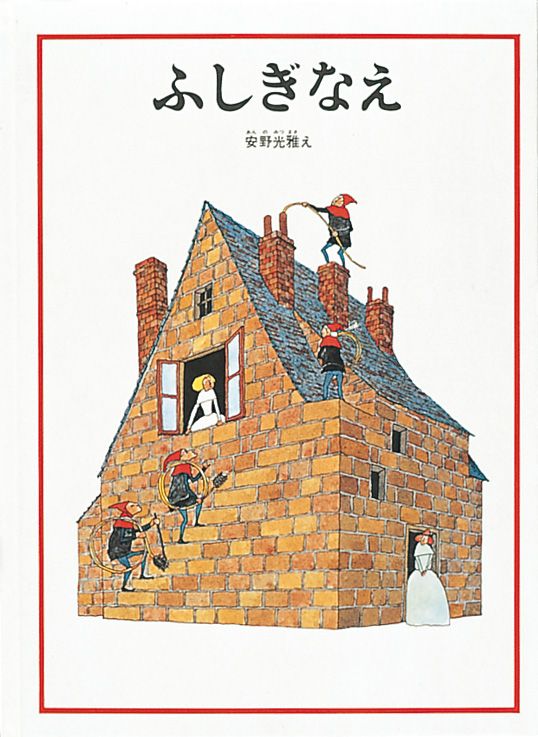
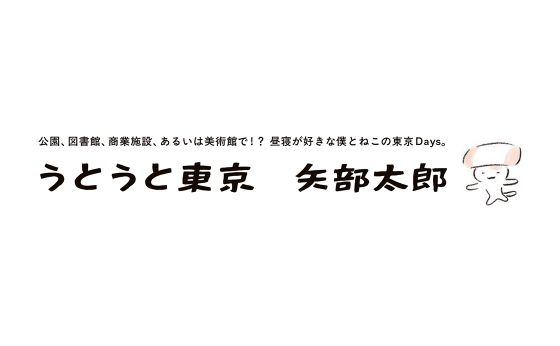
![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)
![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)
![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)
![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)
![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)