女性のココロとカラダのケアを考え、よりよい未来につなげる「Fem Care Project」。本誌編集長・日下紗代子が、さまざまな人にお話を聞きながら、女性の健康課題や働き方について考えていきます。
経済産業省が推進している「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」は、今年で2年目を迎え、来年も継続予定だ。今年度も、私たちフェムケアプロジェクトの「フェムトークコミュニティ」をはじめ、採択を受けた19の事業者が、3月の成果報告に向け、各々の商品やサービスの実証を進めている。国のサポートも強化され、ますます伸張するフェムテック市場だが、このフェムテック推進プロジェクトは、経産省のひとりの女性職員の発案から生まれたものだという。立ち上げの背景や、今後の展望について、経済社会政策室の村山恵子さんにお話を聞いた。
ひとりの女性職員がきっかけとなって生まれたプロジェクト
「きっかけは、女性特有の健康課題について、日本では女性同士でも語られにくいことに対する、ある職員の問題意識からでした。女性にはさまざまなライフイベントがあり、その度に悩みが訪れますが、周囲に共有できず一人で抱え、何かを諦めたり我慢してしまう女性が多いのも現状です。みんなでもう少し課題を共有して、個人ではなく社会として、組織的に女性の健康課題を解決することで、女性の就労継続につなげていくことができるのではないか。そうして立ち上がったのがこのプロジェクトなんです。日本のジェンダーギャップ指数は、146カ国中116位(※1)。なかでも経済分野は女性の参画が進んでいません。就労者に占める女性の割合は半数近くになってきていますが、管理職に占める女性の割合はまだまだです。ここをいかに増やしていくかという命題のもと、これまでも『なでしこ銘柄』(※2)の選定や、民間企業の女性リーダー候補を対象とした研修事業などを進めてきました。そしてさらなる一手として、女性の健康課題に着目し、その課題を取り除くことで女性が活躍できる環境を実現させる別の角度のアプローチに挑戦することにしました」
社会の認知や機運醸成が課題
コミュニティが果たす役割も
令和4年度の採択事業の対象には、新規性、独自性、検証可能かどうかという視点も重視したという。
「2年目の審査では、健康課題に対するよりさまざまな解決方法があることを示すため、新規性、独自性を重視しました。また、フェムテック市場への参入事業者が増えているなかで、まだまだ企業での導入・活用が進みにくいなど、男性の理解や、社会として、女性の健康に向き合うという機運を高めることも同時に必要と感じています。そこで、フェムテックを通じて効果が出ているのかを可視化するため、WHOが出しているプレゼンティーズム(※3)の設問や独自の指標を用いて、女性の健康課題にフェムテックが効いたかを検証することも、採択の条件としました」
フェムトークコミュニティについて村山さんは、「働く女性が自分の健康課題を周囲に共有しづらいという問題意識があるなかで、『フェムトークコミュニティ』はまさにその悩みを共有してみんなで考える場になると思いました。また、健康問題は個人の差も大きいため、私たちも、働く女性はどのような悩みを持っているのか、実際にどのような情報を求めているか、コミュニティを通じて見える化できることや、専門家の先生からの情報提供も含めて、メディアで露出することで、社会に対してより課題意識を高められることが大きなポイントだと思っています」と期待を寄せてくださり、改めて背筋が伸びる気持ちになった。
一方で、働く女性への健康に関する理解はまだまだ道半ば。フェムテック市場に参入する事業者や、受け手である消費者側のリテラシーも重要だ。市場が広まるなか、村山さんは、安全性や信頼性がさらに重要な観点になるという。「さまざまな商品やサービスが出てきているからこそ、専門家の方の視点をしっかり交えて推進しなくてはいけないと思っています。厚生労働省や消費者庁などとも連携をとりながら、どうやって健全なフェムテック市場の発展につなげられるかなどの議論も同時に進めています。個人的には、家庭の中での教育も大事だと思っています」
ひとりの職員の思いから生まれたプロジェクトはいま、高い技術力と多くの思いを持った事業者の夢の実現につながっている。私たちも、そのバトンをつなぐように、ひとりひとりの声に向き合うことが、次なるイノベーションにつながると改めて思った。
※1 出典 内閣府男女共同参画局 男女共同参画に関する国際的な指数 GGI ジェンダー・ギャップ指数
※2 経済産業省と東京証券取引所が女性活躍推進の取り組みに優れた企業を銘柄として選定 (出典 経済産業省 女性活躍に優れた上場企業を選定「なでしこ銘柄」)
※3 欠勤にはいたっておらず勤怠管理上は表に出てこないが、精神面を含め健康上の理由で仕事のパフォーマンスが低下している状態。(出典 産業精神保健研究機構 調査票と活用事例一覧・抜粋 プレゼンティーズムの日本語版調査票)
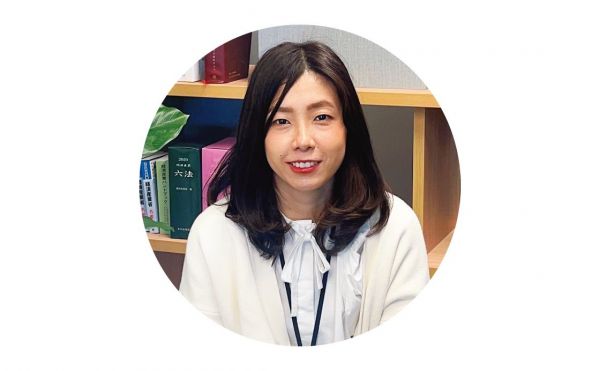
経済産業省経済産業政策局
経済社会政策室室長補佐
村山恵子
大学卒業後、経済産業省入省。2022年6月より現職にて、日本企業におけるダイバーシティ経営や女性活躍の推進に取り組む。

メトロポリターナ編集長
日下紗代子
フェムケアプロジェクトも1周年を迎え、絶賛アップデート中!

Fem Care Project
「フェムケアプロジェクト」は、産経新聞社が主催する、女性の心と身体の「ケア」を考え、よりよい未来につなげるプロジェクト。女性特有の健康課題や働き方について情報発信をしながら考えていく。

https://www.beach.jp/circleboard/af10345/topictitle
経済産業省によるフェムテック推進に関する特設ページ


![theme #12 “フェムテック”というムーブメントが加速しているワケ[フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/7216/3644/7533/metro225_femtalk_hdr.jpg)
![theme #12 “フェムテック”というムーブメントが加速しているワケ[フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/7216/3644/7533/metro225_femtalk_hdr.jpg)

![theme #11 女性にやさしい防災バッグとは?[フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7216/3644/7533/metro225_femtalk_hdr.jpg)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)
![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)
![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)
![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)
![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)