昭和44年に福音館書店から刊行されたせなけいこさんの『ねないこ だれだ』は、赤ちゃんから幼児まで、長年、親子に読み継がれてきた人気の絵本です。
時計が夜の9時を知らせます。「こんな じかんに おきてるのは だれだ?」。ふくろう、みみずく、くろねこ、どろぼう…。「いえいえ よなかは おばけの じかん」。あれ、まだ寝ていない子がいます。「よなかに あそぶこは おばけに おなり おばけの せかいへ とんでいけ」。すると、おばけになった女の子が、白いおばけに手をつながれ、一緒に飛んでいってしまいます。
いろいろな種類の紙を切ったりちぎったりして描かれた貼り絵は、登場人物を際立たせます。特に、夜中に起きているものたちの目は、ギラリと光って表情豊かです。それに対して、女の子の目はどこか夢うつつのようにも見えます。
「寝ないとおばけにされて連れて行かれるよ。だから、早く寝なさい」と、このお話を「しつけ本」にしたい大人は多いのではないでしょうか。
なかなか寝てくれないわが家の息子に、この絵本を読んだときの反応は、私の意表をつくものでした。
「おばけ、いっちゃった。Rくん(自分)もいく!」
女の子がおばけになって、おばけと一緒に飛び立ったその先の世界を、息子は知りたかったのでしょう。大人は、お話から導かれる「だから、〇〇しなさい」を子供に求めがちですが、子供は、せなさんの描いた世界そのものを味わい、面白がり、日常の生活を想像の世界へと広げていきます。絵本の中の女の子の目は、想像の世界を紡ぎ出していく表情なのかもしれません。
一方、娘は「おばけ? いやいや」と怖がるのですが、それでも、この本を繰り返し見たがりました。おばけが登場するたびに、「きゃ~こわい、こわい」と家族に体をすり寄せ抱き着きました。安心できる人と一緒なら、怖さも、それを乗り越える跳躍や面白さに変わるのです。
そのうち、娘の反応とそのかかわりがおかしくて、親子で「きゃ~きゃ~」と、まるで、肝試しのような興奮状態で大騒ぎです。娘は寝てなんかいられません。私は、この絵本は“昼間”に子供と思いっきり“夜の世界”を楽しむ絵本ではないかと思うようになりました。
『ねないこ だれだ』を「しつけ本」にしてしまうのはもったいないことを、子供たちが教えてくれるのです。(国立音楽大教授 林浩子)




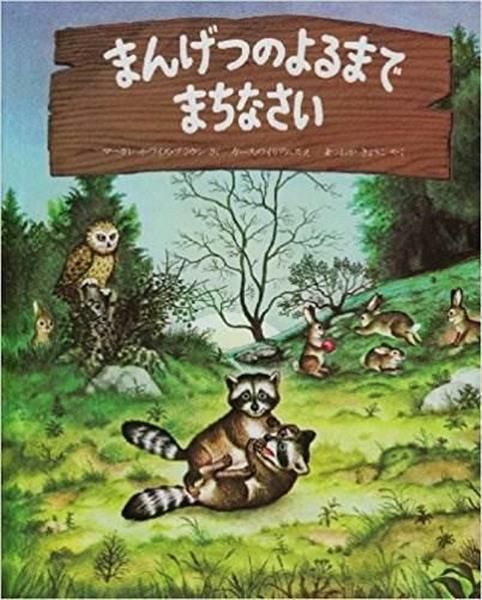
![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)
![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![自宅で踏み出す第一歩[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2617/6784/9324/metro275_special_04_hdr.jpg)
![香道/合気道[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2217/6784/7337/metro275_special_03_hdr.jpg)
![書道/華道[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2617/6784/6608/metro275_special_02_hdr.jpg)