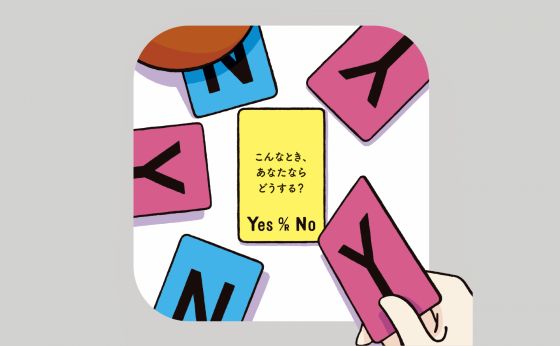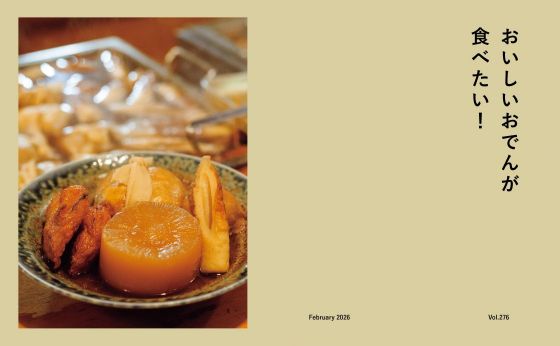もしものときのことをみんなで考えることで、新しい発見や気づきが生まれるかもしれない。このページでは、リッジラインズがファシリテーターとなりさまざまな領域で活躍する人たちを招き、「クロスロード」を実践!4つの問いについて意見を交わしたなかから、とくに盛り上がりを見せたディスカッションの様子を紹介する。一緒に「正解のない問い」を考えながら、学びを深めていこう。

〜Game Player〜
1. メトロポリターナ編集長 日下紗代子
2. リッジラインズ 上席執行役員Partner 西田武志さん
3. リッジラインズ D&I推進室 今井智香さん
4. リッジラインズ 総務 福井 誠さん
5. 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 川﨑 愛さん
6. コニカミノルタ MELON事業責任者 川﨑 健さん
7. 産経新聞 記者 篠原那美さん
8. ヤフー SR推進統括本部 災害支援推進室 室長 安田健志さん
9. リッジラインズ D&I推進室 藤田なつみさん
10. リッジラインズ Director 川嶋孝宣さん
〜Game Rule〜
1)参加メンバーは、問いに対して「自分ならどうするか?」を考え、YESとNOのどちらのカードを出すかを決める。
2)全員が同時にカードの答えを見せ、多数派の意見であった人は「青い座布団」を1枚もらうことができる。
3)ゲーム終了後、いちばん多くの座布団を持っていた人が勝利。
★少数派であっても、メンバーの中で1人だけが異なるカードを出した場合、その人は「金の座布団」を受け取ることができる。
〜Question〜
Q1. 被災地から自宅に徒歩で向かう途中、コンビニに寄ると陳列棚の商品が少なくなっており、なかでも飲料はペットボトルの水2本のみ。
2本とも買う?
Q2. 地震が発生して近所の小学校に避難したが、避難所内は大混乱している。
仕切り役として手を挙げる?
Q3. 現在、深夜12時。近くの川に氾濫・浸水の危険があるとして避難勧告が発令されたことを防災無線で知った。しかし、家では子供が熱を出して寝ている。
いますぐ避難を始める?
Q4. 避難所で1人で受け付けをしているとき、車椅子を利用している人が1人で避難してきた。その避難所の車椅子対応トイレは壊れて使えない。
この避難者を受け入れる?
《Question》
被災から自宅に徒歩で向かう途中、コンビニに寄ると陳列棚の商品が少なくなっており、なかでも飲料はペットボトルの水2本のみ。
2本とも買う?

Yes
福井さん)自分のために2本買うのではなく、本当に困っている人を見かけたときに分けてあげられるよう、2本とも買う選択をすると思います。もしかしたらその先のコンビニにたくさん在庫があるかもしれないけれど。自分が手に入れられる状況のときには、なるべく手に入れておきたいと思いました。

Yes
安田さん)まわりに買いたい人がいなかったら、家族のことを考えて2本とも買います。災害発生時、自分が助かるかわからないことに加えて、家では家族も待っている。緊急時にはやはり、自分と家族を優先的に考えてしまうと思います。

Yes
日下)私自身はまだ比較的若くて体力もあります。であれば、いま水が手に入る状況ならば確保しておいて、その先で本当に必要としている人に出会ったときに渡したり、その場にいる人たちでシェアしたり、といった方法を考えたいと思いYESにしました。1本よりも複数本あったほうが、助け合いの輪を広げやすい。自分のためにも、ほかの誰かのためにも、手に入るものはそのときに手に入れておきたいなと考えました。

Yes
川嶋さん)私たちはさまざまな災害を経験して学んだことで、数日生き延びるのに困らない最低限の備蓄は、一定の常識になりつつあります。加えて、そのときコンビニの棚が空だとしても、日本の災害対応や物流は年々進化しているから、商品棚にモノが戻るまではそう遅くないだろうと考えられる。「この状況で自分が2本買っても大丈夫だろう」という安心感もあり、目の前にある2本を自分や家族のために買う選択肢を選びました。

No
川﨑愛さん)先日、家族でキャンプに行ったのですが、運悪く強い雨が降っていて、遭難するのではないかと思うほどの荒天でした。そんなときに、「限られた材料をみんなでシェアしてどうにか生き延びられないか」という思考回路になって。いまあるもので少しずつつないでいく必要があるからこそ、私が買い占めるのではなく次に手に取る人の分も残しておいてあげたいと思いました。最近のキャンプの経験があったからこそ、このような考えになったのかなとも思います。
多数派と少数派、
両方の考え方を知ることが大切!
被災下で数少ない飲料水が2本だけ店頭に並んでいたら…。きっと多くの人が2本とも手に取るだろう。リッジラインズの川嶋さん率いるチームでも2本買う選択が多数派のなか、川﨑さんはただ1人、「買わない」ことを選び、「金の座布団」を得た。その理由を次のように話す。「いまは自宅に水や食料などを備えているため、買えなくてもある程度はしのぐことができます。自分以外の必要としている方のためにも、我慢したほうがいいと思いました」。川嶋さんはこう続ける。「3.11を経て、人々は備えに対して真剣に考えるようになりました。経験から学び、情報を正しくとらえることの重要性をあらためて感じますね」。
そもそも、なぜ1人だけ異なる意見のときに「金の座布団」がもらえるのか? クロスロードのルールについてあらためて考える場面も。安田さんは次のように推察する。「視点の多様さに気づくこと、少数派の意見にも耳を傾けることを尊重するためのものなのかなと思いました」。川嶋さんも次のように続ける。「このゲームに限らず、こうした場面は多いと思います。たとえば会議中、多数派の意見一色になって盛り上がってしまい、少数派が意見を言いにくくなってしまうこともありますよね。少数派にスポットを当てる意味で、金色の座布団の存在は、発言を促すいい機会になりますね」。
じつは、YESを選んだ理由もさまざま。川嶋さんと安田さんは「やはり自分と家族のために確保したいという気持ちが強い」、福井さんと日下編集長は「自分以外の誰かが困っているときに分けてあげられるように自分が買っておく」と回答した。「結論は同じであっても、選んだ理由や背景は違うこともあります。YESとNOの違いのみならず、一人ひとりの意見の違いを知ることで得られる発見もありました」と川嶋さんは総括する。
YESとNO。問いに対する答えは二択だが、その答えに至る考え方は人それぞれ。話し合いをしながら互いの考えを理解することが、防災において多様な視点をもつことにつながっていくのかもしれない。



![正解のない問いを考えること①[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/1616/9406/1530/metro247_special_03_hdr.jpg)
![正解のない問いを考えること①[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/1616/9406/1530/metro247_special_03_hdr.jpg)

![想像しよう、もしものこと[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3916/9405/9869/metro247_special_01_hdr.jpg)
![よりよい防災を考えるために[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7916/9406/1349/metro247_special_02_hdr_b.jpg)