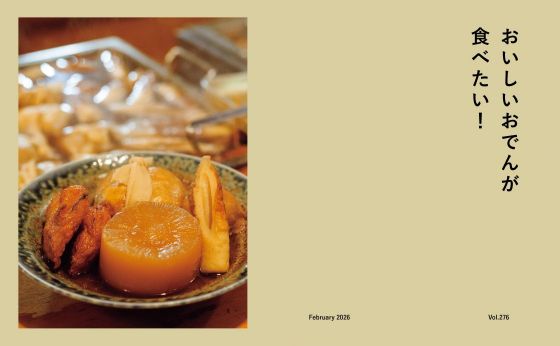もしものときのことをみんなで考えることで、新しい発見や気づきが生まれるかもしれない。このページでは、リッジラインズがファシリテーターとなりさまざまな領域で活躍する人たちを招き、「クロスロード」を実践!4つの問いについて意見を交わしたなかから、とくに盛り上がりを見せたディスカッションの様子を紹介する。一緒に「正解のない問い」を考えながら、学びを深めていこう。
《Question》
地震が発生して近所の小学校に避難したが、避難所内は大混乱している。仕切り役として手を挙げる?

Yes
篠原さん)1人のリーダーが旗を振って決断しなければならない、ということでもない気がします。避難所では「不自由を感じながらも声を出せない人たちがただ我慢し続けるしかない」という状況が起こることも容易に想像できてしまう。だからこそ、「その方向だけで大丈夫ですか」「こういう視点も必要ですよね」と多様な声を代弁するために、自分もその意思決定チームの中に入らなければならないと思うんです。1人では決められなくても、複数人のうちの1人として、仕切る人たちの中に切り込んでいく必要があると思ってYESにしました。

Yes
今井さん)私自身には子供や介護が必要な家族がいないので、日常でも非日常でも身軽に動けるのです。自分1人だったらなんとでもなるからこそ、公平に判断ができるかということよりも、むしろ「自分のような立場の人を労力として使ってもらったほうがいいだろう」と判断して手を挙げるだろうと思いました。

Yes
西田さん)いろんな判断が迫られる局面だからこそ、「自分の判断によって誰かを怒らせたとしても引き受ける自信があるか」という覚悟が求められるでしょう。私はいまの組織においても剛腕でみんなを引っ張っていくタイプではないけれど、感情的になることもあまりないので、みんなの精神面でも柱のような存在にはなれるかなと思い、YESにしました。

No
藤田さん)たとえば子供のケアひとつとっても、理由があってケアが手厚くなっているとわかっていても、「その子も大変かもしれないけど、うちの子も大変なのに…」と少なからず感じてしまうと思う。非常時であればなおさら、自分の子供をいちばんに考えてあげたいという気持ちが強くなりますよね。「大混雑の非常時、冷静に仕切り役として公平性を保てるか?」ということに自信が持てません。
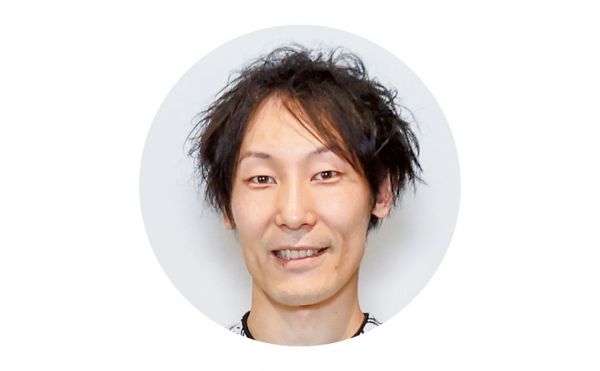
No
川﨑さん)正解のない問いに対しては、すべての意見を反映できないからこそ「7割が賛同してる意見だったら3割の意見は切り落とそう」といった決断をしなければならないわけですよね。たとえば「生きるか死ぬか」という究極のジレンマがあるとしたら、「みんなのことを考えたら、7割の人が生き残る選択をしたほうがいい。申し訳ないけど3割の人は諦めてください」と言わないといけない。でも、もし自分の家族がその3割に入っていたら猛反対しますよね。「あなたからすれば3割のうちの1人に過ぎないかもしれないけど、僕にとってはかけがえのない存在なんだよ!」って。自分ごとになると納得できないのに、少数派に「諦めてください」と言うことは、自分にはできないと思いました。
リーダーは1人でなくていい。
チームの一員として手を挙げよう。
災害が発生し、自分や家族の安全な生活が危ぶまれる状況下。不特定多数の人々が集まる避難所で、強い意志をもってリーダーシップを発揮すべきかは、判断が分かれるだろう。リッジラインズの今井さん率いるチームでは、YESが3人、NOが2人という結果に。自身のこれまでの経験や立場によっても、答えは異なってくるようだ。
「自分に子供がいたらNOと答えるかもしれない」と話すのは、YESの札を出した今井さん。「そのときは自分の子供を守ることに精一杯だから、仕切り役なんてとても考えられないと思います。いまは自分ひとりでいかようにも動ける状況だからYESと判断ができたのかも」。それに対して、藤田さんも次のように続ける。「たしかに、問いに対する答えを考えるとき、誰もが無意識にいまの自分のバックグラウンドに影響を受けるから、そのときの状況によっても、答えは変わってくる気がします。10年前の私だったら迷わずYESと答えたかもしれない」。
ゲーム終了後には、「非常時に重要な決断を下す責任は大きい。だからこそ、自分1人が先頭に立つのではなく、みんなでチームをつくることが大切だ」という結論に。篠原さんは次のように話す。「自分も不安ななか、1人でみんなをまとめていくのは精神が保たない。多様な人々が自分の得意分野を持ち寄ってチームをつくることが大切だと思います。これまで培ってきた経験やキャリアは、そうした場でもどこかでいきるはず」。藤田さんも続ける。「誰か1人に委ねてしまうとその決断は重たいし、さまざまな意見を持つ人が集まる避難所では、リーダーの責任ばかり問われてしまう可能性もあります。だからこそ、チームになってそのときの解決策をみんなで一緒に探すことが重要なのかもしれないですね」。
仕切り役は1人でなくてもいい。この状況をよくしようと手を挙げた者同士で手を取り合えば、よりよい解決策へと導く決断ができるのだろう。


一人ひとりの立場から
よりよい防災を考える。
2つの問いから意見を出し合い、さまざまな議論が繰り広げられたクロスロード。コニカミノルタで医療用AI通訳の事業責任者を務める川﨑健さんは、異文化コミュニケーションの重要性についても触れる。「災害時に外国人にも円滑に医療を提供するには、宗教上の理由からヒジャヴ(スカーフ)で顔を隠している方への配慮や、ハラール、礼拝場所の設置等が重要になります。単に会話を通訳するだけでなく、多様な人々が協力しあうためのコミュニケーションが大切です。今回の議論には、それに通ずるものを感じました」。ヤフーで防災事業に従事する安田さんは、次のように続ける。「人とのつながりが共助や互助となっていきますよね。ヤフーは10月にLINEと統合します。これまではメディアとしての情報配信が中心でしたが、LINEというコミュニケーションツールが加わることによって、人々のコミュニティの構築に貢献できるかもしれない。時代の変遷にともない薄まりつつあるコミュニティの力を、もっと活性化させていきたいです」。
長年D&I活動に携わってきた今井さんは、D&Iと防災の関係について次のように話してくれた。「誰もが被災者になる可能性があります。だからこそ、『もし自分がこの立場になったら』と想像力を膨らませ考えることができる。相手の立場になって本気で考えてみると、自分の偏った考え方に気付くことができるんです。『そのときその場でみんなで正解をつくる』という防災の考え方とD&Iは実はとてもよく似ています」。
さまざまな立場の人が集い、真剣に考えを巡らせたからこそ上がったこれらの意見。こうした問いに、あなただったらどちらの札を出し、どのように話し合いに参加するだろう? 自分と周りの大切な人たちの生活を守るためにも、あらためて防災について考えてみたい。


全体監修:京都大学防災研究所 教授 矢守克也
お問い合わせ:Ridgelinez株式会社
https://www.ridgelinez.com

![正解のない問いを考えること②[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/2716/9406/2661/metro247_special_04_hdr.jpg)
![正解のない問いを考えること②[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/2716/9406/2661/metro247_special_04_hdr.jpg)

![正解のない問いを考えること①[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1616/9406/1530/metro247_special_03_hdr.jpg)
![よりよい防災を考えるために[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7916/9406/1349/metro247_special_02_hdr_b.jpg)
![想像しよう、もしものこと[みんなで考えよう、防災のこと]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3916/9405/9869/metro247_special_01_hdr.jpg)